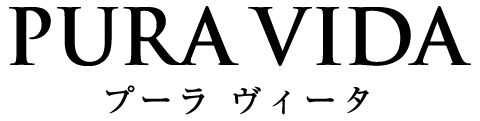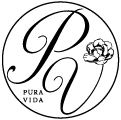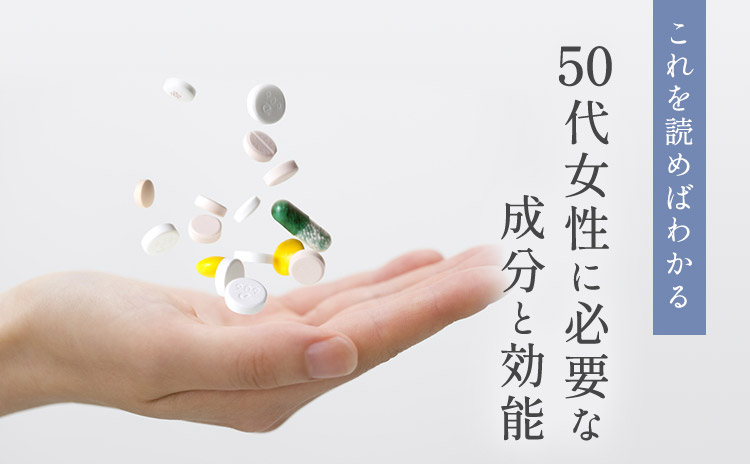「なんだかずっとお腹の調子が悪い」
「最近よく聞く腸内フローラって何?」
「腸活って何から始めたらいいの?」
第二の脳とも言われる腸の調子は、全身の健康状態に影響します。
中でも腸内細菌の集まりを指す「腸内フローラ」は非常に重要な役割を担っています。
とはいえ「なんでそんなに腸は重要なの?」「腸内フローラってそもそも何?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では以下の内容について解説します。
| この記事でわかること |
|
快適な毎日を送るために非常に重要な内容なので、ぜひ最後までお読みください。
目次
腸内フローラとは?基礎知識と5つの役割を簡単に解説

腸内フローラとは腸内細菌の集まりのことで、正式名称は腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)といいます。
腸内細菌が塊となって腸の壁に隙間なく張り付いている様子が、花畑のように見えることから名付けられました。
腸内フローラの形成パターンに最も大きな影響を与えるのは、母親の腸内環境の母子伝播で、その後の生活習慣も密接に関わります。
こちらでは、腸内フローラの役割をわかりやすく解説していきます。
- 食べ物の消化
- 免疫の活性化
- ビタミンの生成
- 有害物質の解毒
- 腸のぜん動運動の促進
腸内フローラについて理解し、健やかに保つことは、からだ全体の健康維持に不可欠です。ぜひ最後まで確認してくださいね。
1-1. 食べ物の消化
腸内フローラは、そのままでは人体が消化できない食物繊維やオリゴ糖などの物質を発酵させて、短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)を生成し、消化できるようにします。短鎖脂肪酸は腸の細胞のエネルギー源となり、健康維持において非常に重要です。
また、腸内フローラに含まれる善玉菌には消化吸収を助け、栄養素の利用効率を高める働きがあります。
1-2. 免疫の活性化
腸内フローラは、体内の免疫細胞の約70%が存在する「腸管免疫系」の調節を担います。
腸内フローラによって作り出された短鎖脂肪酸は、過剰な免疫機能を抑制しながら病原菌の侵入を防ぐ役割を持っており、免疫の活性化・維持に不可欠です。
腸内フローラは免疫システムの適切なバランスを維持するために非常に重要で、健やかに保つことで、さまざまな感染症や免疫関連疾患のリスクを下げられるでしょう。
1-3. ビタミンの生成
腸内細菌は8種類のビタミンB群と、ビタミンKを生成します。ビタミンKは血液凝固や骨の健康維持に重要な役割を果たし、ビタミンB群は以下のような役割を持ちます。
- エネルギー代謝の促進
- 神経機能の維持
- DNA合成
これらのビタミンを取り込むことは、生きていく上で必要不可欠といえるでしょう。
さらに、人間はビタミンを生合成できないため、食事や腸内細菌から摂取する必要があります。健康維持には、腸内環境を安定させてビタミンの産生量を保つことが重要です。
| 参考: | 腸内細菌によるビタミン産生 |
| ビタミン産生のメカニズムについて |
1-4. 有害物質の解毒
乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌は発がん性物質を分解し、肝臓の解毒負担を軽減する働きがあります。とくにアンモニアや硫化水素などの有害物質の中和には必要不可欠です。
腸内フローラによって有害物質が解毒されることで、安全に不要な物質を排出できるようになります。
1-5. 腸のぜん動運動の促進
ぜん動運動(ぜんどううんどう)とは、腸が波のように収縮することです。ぜん動運動を繰り返すことで、食べ物や老廃物を体外に送り出します。適切に食べ物の消化吸収を行うために必要な運動です。
腸内フローラ内の善玉菌が産生する短鎖脂肪酸は腸の神経を刺激し、消化管運動を活性化させます。消化管運動が活性化されるとぜん動運動が促進されるので、老廃物排出が促されます。
腸内フローラは、体内の老廃物排出における重要な役割を担っているといえるでしょう。
腸内フローラに含まれる3つの細菌と最適なバランスを解説

腸内フローラは、以下の3種類の細菌で構成されています。
- 善玉菌
- 悪玉菌
- 日和見菌
3種類の細菌のバランスによって腸内フローラの環境が変わり、健康状態に影響を及ぼします。そのため、最適なバランスを保つことが健康維持には大切です。
それぞれの働きについて詳しく確認していきましょう。

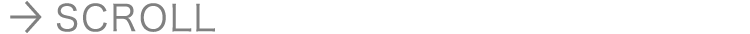
| 腸内細菌の種類 | 代表的な細菌 | 役割 | 適切な割合 |
| 善玉菌 |
|
|
2割 |
| 悪玉菌 |
|
|
1割 |
| 日和見菌 |
|
|
7割 |
2-1. 善玉菌
乳酸菌・ビフィズス菌に代表される「善玉菌」は、腸内で発酵活動を行う細菌で、腸内フローラ内で2割を占める状態が適切です。悪玉菌の増殖や定着を抑制し、腸内環境を健康に保ちます。
健康のためには、善玉菌を悪玉菌よりも多く保つことが非常に重要です。ヨーグルトや納豆など、善玉菌が多く含まれている食材を積極的にとって腸内フローラのバランスを保ちましょう。
2-2. 悪玉菌
ウェルシュ菌・黄色ブドウ球菌に代表される「悪玉菌」は、腸内で腐敗活動を行う細菌です。腸内フローラ内では1割を占める状態が適切とされています。
悪玉菌が善玉菌よりも増えると、以下のようなトラブルを引き起こします。
- 便秘
- 下痢
- 肌荒れ
- アレルギー
ただし、悪玉菌は肉類などのタンパク質を分解する際に必須で、不要な細菌ではありません。適切なバランスを保つことが重要だと考えましょう。
2-3. 日和見菌
バクテロイデス、大腸菌に代表される「日和見菌(ひよりみきん)」は、腸内で最も多くを占める細菌です。多くは未知の細菌で、状況によって善玉菌もしくは悪玉菌と同じような働きをします。
適切な割合は7割とされており、善玉菌と悪玉菌のうち、数が多い方の味方をします。そのため、善玉菌の方が多い状態を保たないと、悪玉菌の悪い働きが強く影響を及ぼしてしまうことに注意しましょう。
腸内フローラが乱れる5つの原因

「気をつけているのに腸内環境が整わない」という方のために、こちらでは腸内フローラが乱れる原因を解説します。
- 食生活
- 不規則な生活
- 運動不足
- 加齢
- 便秘
腸内フローラを保つためには、乱れる原因を知ることが効果的です。それぞれ詳しく確認していきましょう。
3-1. 食生活
毎日の食事は、腸内フローラに最も大きな影響を与えます。例えば以下のような食事は悪玉菌の増殖を促し、腸内フローラのバランスを悪化させてしまう可能性があります。
- 脂質が多い
- タンパク質が多い
- 食物繊維が少ない
とくに、肉類中心の食生活は悪玉菌の活動を活発にするため、他の食材もバランスよく取り入れましょう。
3-2. 不規則な生活
睡眠不足や不規則な生活リズムは、自律神経のバランスを崩します。腸の蠕動活動や消化液の分泌量を低下させるため、腸内フローラの働き抑制に直結します。
また、体内時計が狂ったり不規則な生活によってストレスが増えたりすると、腸内フローラのバランスも崩れるため、注意が必要です。
3-3. 運動不足
適度な運動は腸のぜん動運動を促進するため、良好な便通を保つために重要です。運動量が不足すると腸の動きが低下し、便秘などの問題を引き起こします。
便秘が起きると腸内に老廃物が滞留するため、悪玉菌が増殖します。腸内フローラのバランスが乱れることにつながるため、日々適度な運動量を確保するようにしましょう。
3-4. 加齢
日々の生活習慣に加え、加齢も腸内フローラのバランスを乱す原因の1つです。加齢に伴って自然と腸内の善玉菌の割合が減少し、悪玉菌が増加する傾向があります。
歳を重ねても以前と変わらない不規則な生活を送っていると、腸内フローラのバランスが乱れ、消化機能や免疫力の低下などの問題につながる可能性があります。とくに40代後半を過ぎたら、意識的に腸内環境を整える習慣をつけることが大切です。
3-5. 便秘
便秘が起きると腸内に老廃物が長時間滞留するため、悪玉菌の増殖を促進します。悪玉菌の増殖により有害物質が生成されるため、腸内フローラのバランスが崩れてしまいます。
さらに、便秘が慢性化すると、腸壁への刺激が増えることで炎症を引き起こすリスクが高まるため、早めに対処するようにしましょう。
また、便秘は肌荒れの原因にもなります。肌荒れに悩んでいる、という方は以下の記事も参考にしてみてください。
便秘によって肌荒れが起こる理由3選と5つの改善方法!サプリメントの選び方も解説
腸内フローラが乱れると起こる3つの不調を解説
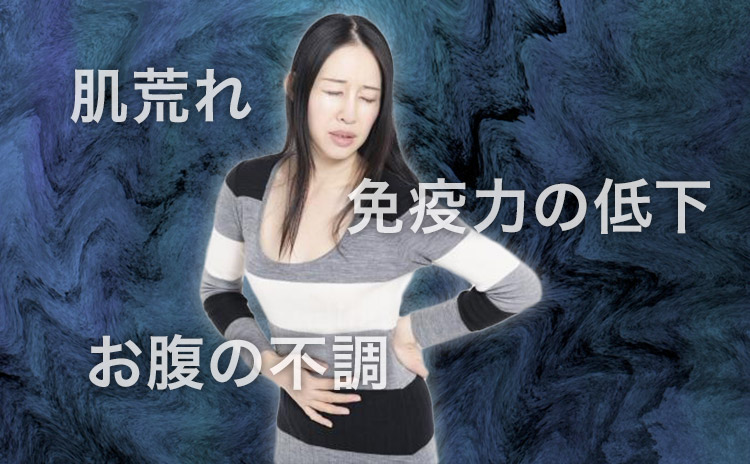
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、体にとって重要な役割を担っています。そのため、腸内フローラが乱れると心身にさまざまな不調が発生します。
「なぜか身体の調子が悪い…」と感じるときは、腸内環境が乱れているのかもしれません。
こちらでは、腸内フローラが乱れることによって起こる不調を解説します。
- お腹の不調
- 肌荒れ
- 免疫力の低下
それぞれ詳しく確認していきましょう。
4-1. お腹の不調
腸内フローラが乱れ、悪玉菌が増えると大腸のぜん動運動が弱くなり、有害物質が発生します。ぜん動運動が弱まると便通が悪くなり、以下のような症状が現れます。
- 便秘
- 下痢
- おならの増加
- お腹の膨満感
- 腹痛
慢性的な不快感を抱えることとなり、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。お腹の不調を感じたら、すぐに腸内環境の乱れを疑って対処するのがおすすめです。
4-2. 肌荒れ
腸内フローラが乱れて老廃物の排出が適切に行われなくなると、肌の状態にも悪影響を及ぼします。
腸内で発生した有害物質が血液を通して体内に循環することで、以下のような肌荒れが引き起こされます。
- ニキビ
- かゆみ
- 乾燥
- くすみ
- アトピー性皮膚炎の悪化
- テカリ
スキンケアを適切に行っているにも関わらず肌荒れが改善しない、という場合は腸内フローラの乱れが原因かもしれません。普段の生活等を見直してみましょう。
4-3. 免疫力の低下
腸内フローラは免疫細胞の産生や維持に深く関与しています。そのため、バランスが乱れると免疫力が弱くなり、以下のような不調を引き起こします。
- 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる
- アレルギー症状が悪化する
- 口内炎ができやすくなる
- 疲れやすくなる
病気にかかりやすく、治りにくい状態になってしまうので、普段から腸内環境を整えて免疫力を維持できるよう意識しましょう。
腸内フローラを整える「腸活」方法5選

「腸内フローラを整えるにはどうしたらいいの?」という方のために、こちらでは「腸活」におすすめの方法を解説します。
- 発酵酵素を摂取する
- 運動習慣をつける
- ストレスを解消する
- 腸内環境に良い食べ物を食べる
- 十分な睡眠を確保する
それぞれ詳しく確認していきましょう。
5-1. 発酵酵素を摂取する
発酵食品には、乳酸菌などの善玉菌が豊富に含まれています。
善玉菌を増やすことは腸内フローラを健全に保つことに直結するので、積極的に発酵食品を食べることを心がけましょう。
とくに、発酵酵素は発酵食品の中でも吸収力・栄養力が高いため、効率的に善玉菌を増やせるので非常におすすめです。
「発酵酵素を効果的に摂取したい」という方は、サプリなどで摂取するといいでしょう。
サプリメントであれば手軽に十分な量の発酵酵素を摂取できるので、腸内フローラを整え、健全に保つために非常に効果的です。
5-2. 運動習慣をつける
適度な運動は腸のぜん動運動を促進させるため、腸内フローラを整えるのに非常に重要です。
ぜん動運動が適切に行われることで便通が良好に保たれ、有害物質の発生が抑制されます。
実際に、運動を習慣化させたマウスの腸内細菌を移植したマウスは、エネルギー代謝が高まり、善玉菌を増やすことに貢献したことが示されました。
| 参考: | 「腸内環境と骨格筋代謝のコミュニケーションに着目した運動効果の実験的・疫学的検証」 |
5-3. ストレスを解消する
ストレスは自律神経のバランスを乱して腸の機能を低下させ、腸内フローラの乱れを引き起こします。さらに、腸内フローラの乱れが慢性化すると、精神疾患などに発展するおそれもあります。
リラクゼーションや趣味の時間を持つなどして、日常的にストレスを溜め込まないようにしましょう。
| 参考: | 腸から脳の健康を考える ビフィズス菌A1株による認知機能改善作用 |
5-4. 腸内環境に良い食べ物を食べる
毎日の食事も、腸内フローラに大きな影響を与えます。善玉菌そのものである乳酸菌やビフィズス菌、善玉菌の餌となる食物繊維を積極的に摂取することを心がけましょう。
効率的に腸内フローラを整えたいという方は「腸内フローラのバランスを改善することによって宿主の健康に好影響を与える生きた微生物」である、プロバイオティクスを含む食事もおすすめです。
5-5. 十分な睡眠を確保する
睡眠不足や睡眠リズムの乱れは、自律神経の乱れを引き起こし、腸内環境の悪化に直結します。十分な睡眠を規則的にとることを普段から意識しましょう。
実際に、睡眠不足は腸内フローラの破綻を誘導し、短鎖脂肪酸の生成量を低下させることが示されています。
| 参考: | 睡眠不足が腸内細菌叢を乱すメカニズムを初めて解明~αディフェンシンによる睡眠障害の改善に期待~:北海道大学 |
腸活を正しく行うことで腸内フローラが整い、快適な日常生活を送ることにつながります。
腸内フローラのバランスを整えるには発酵酵素がおすすめ

腸内フローラのバランスを整えるためには、腸内の善玉菌を増やすことが非常に効果的です。
発酵食品は、乳酸菌をはじめとして腐敗物質の増加を抑制する善玉菌が豊富に含まれているため、積極的に毎日の食事に取り入れましょう。
特に「発酵酵素」は善玉菌が豊富に含まれているだけでなく、吸収率が高いという特徴もあるため、効率的に腸内フローラのバランスを整えられます。
とくに、以下の3つの特徴を持った発酵酵素は高い効果が望めます。
- 新鮮な野草、野菜、果物で作られている
- 長期の発酵・熟成で吸収されやすくなっている
- 余分な添加物が入っていない
さらに、より根本から自身の健康を見直したいという方には東洋医学をベースとした製品を取り入れるのがおすすめです。
東洋医学では、不調を改善して健康的な体を作っていくには「不調を引き起こす原因にアプローチして、心身のバランスを整えていくこと」を重視しています。
東洋医学をベースとした発酵酵素サプリメントなどもあるので、忙しい方でも毎日の習慣に取り入れやすい点も魅力です。
腸内フローラを理想の状態で保ち、毎日をいきいきと過ごしたいという方は、ぜひ検討してみてくださいね。
まとめ
腸内フローラは消化吸収に限らず、免疫維持などさまざまな役割を担っています。
腸内フローラのバランスが崩れると、多くの不調が現れるため、腸内フローラを理想の状態に保つことは、全身の健康維持において非常に重要です。
普段から腸内フローラに良い習慣をつけることで、快適な毎日が送れるでしょう。
バランスのよい食事や適度な運動を習慣づけて、腸内フローラを理想の状態で保てるよう意識してみてくださいね。
「なかなか忙しくて生活改善に手が回らない」という方は、手軽に取り入れられる発酵酵素サプリメントなどもおすすめです。
簡単に取り入れられる美容と健康習慣で、5年後も10年後も美と健康を維持しましょう。